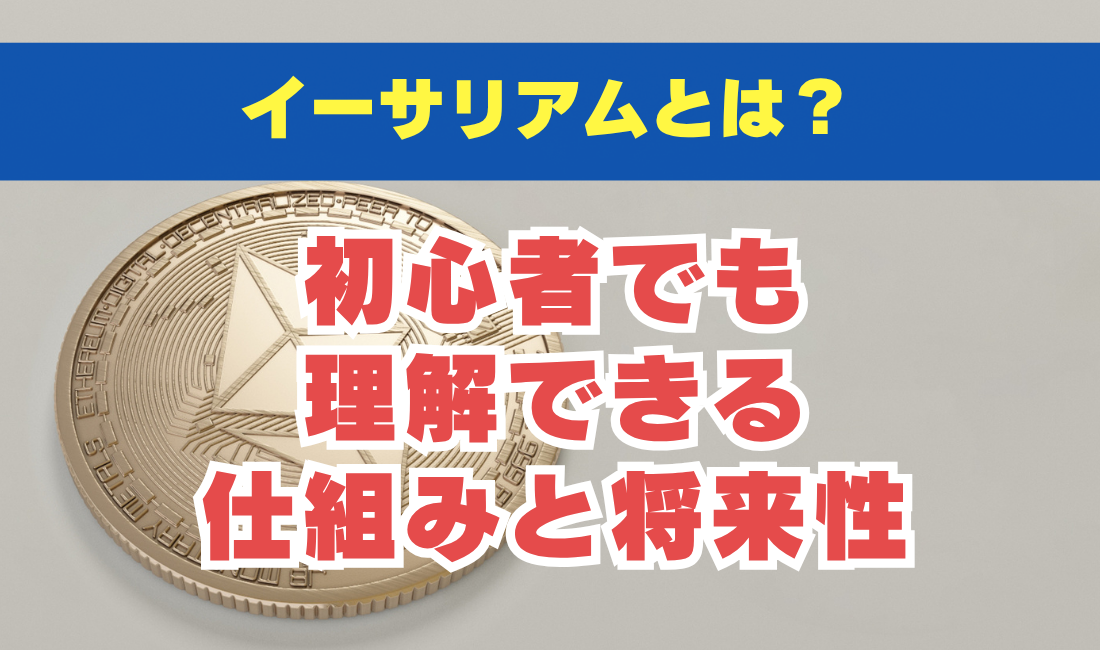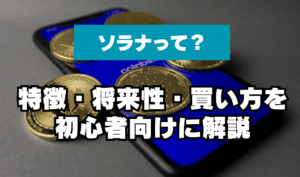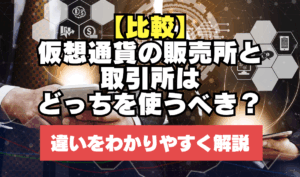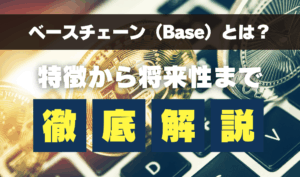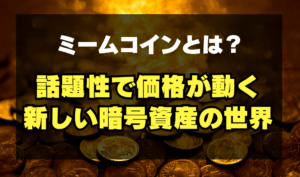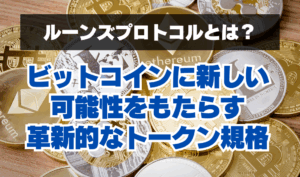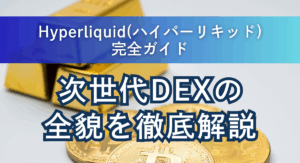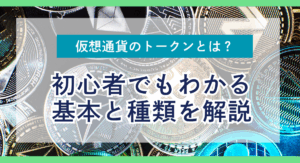「イーサリアムって何なの?」
「ビットコインとどう違うの?」
「投資してみたいけど、リスクは大きいの?」
こうした疑問をおもちの方も多いのではないでしょうか。イーサリアム(Ethereum)はビットコインと並んで有名な仮想通貨です。
ただし、その価値は「通貨」としてよりも「有能な仕組み」にあります。
サービスを動かす土台として機能し、NFTやDeFiなどで活用されている点が特徴です。
この記事では、以下の内容について解説します。
- 初心者でもわかるイーサリアムの基礎知識
- メリットとデメリット
- 将来性や今後の注目ポイント
- 安全に扱うために注意点
イーサリアムの特徴や仕組みを知り、投資してみようと考えている方はぜひ最後までお読みください。
イーサリアムとは?初心者でも理解できる基礎知識
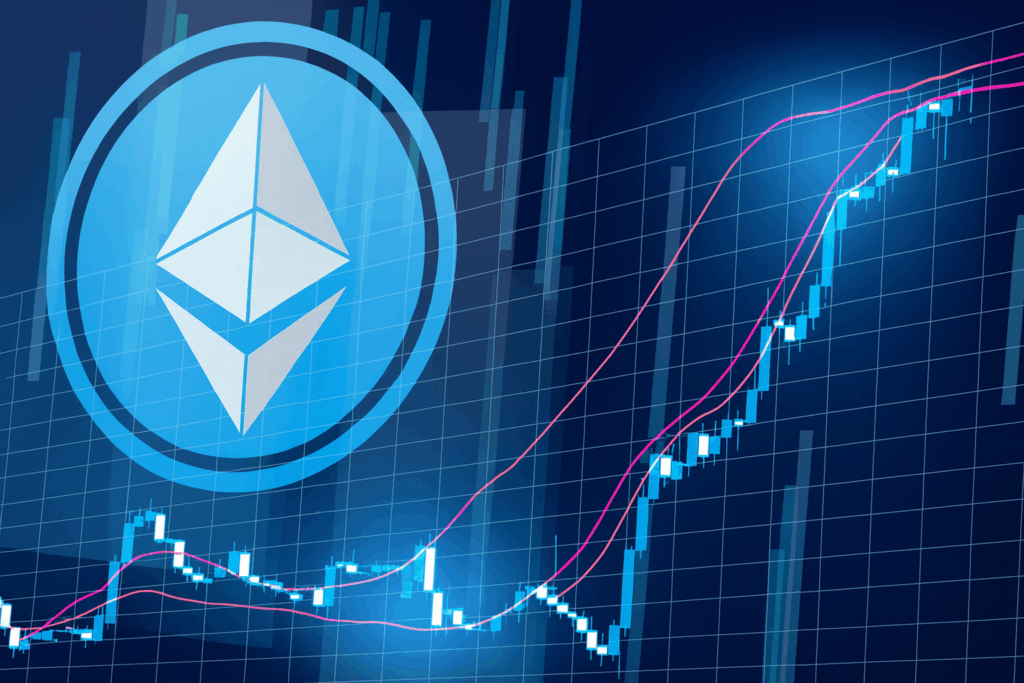
イーサリアムは、ビットコインと並ぶ代表的な仮想通貨です。ただし、役割は大きく違い「通貨」としてよりも、サービスを動かすための「基盤」として力を発揮しています。
ここでは、イーサリアムに関する3つの基本を解説します。
- イーサリアムは「アプリを動かせる仮想通貨」
- イーサリアムとイーサ(ETH)の違い
- ビットコインとの役割の違い
それぞれについて、初心者でもイメージしやすい形で解説していきます。
イーサリアムは「アプリを動かせる仮想通貨」</h3>
イーサリアム(Ethereum)は、単なる「お金」としての仮想通貨ではなく、アプリケーションを動かせる仕組みをもっている点が大きな特徴です。
ビットコインが「デジタルゴールド」と呼ばれ、主に価値の保存として利用されるのに対し、イーサリアムは「アプリを動かすためのプラットフォーム」として注目されています。
その土台となっているのがブロックチェーンです。
| 【ブロックチェーン】 取引データを「ブロック」として時系列につなげ、世界中の参加者で共有することによって、改ざんを防ぎ安全に記録できる仕組み |
イーサリアムはこのブロックチェーンに「スマートコントラクト」と呼ばれる、自動で契約や取引を実行できる仕組みを組み込んでいます。
これにより、人の手を介さずにアプリやサービスを安全に動かすことが可能になったのです。
たとえば
- NFTの売買
- 分散型金融(DeFi)
と呼ばれるサービスは、すべてこの仕組みの上に成り立っています。
初心者が知っておくべきなのは、イーサリアムが「通貨として使える」だけではなく「サービスの基盤」になっているという点です。
この広がりこそ、世界中で注目を集める理由の一つといえるでしょう。
イーサリアムは「プラットフォーム」イーサ(ETH)は「通貨」
イーサリアムという言葉はしばしば「仮想通貨」と同じ意味で使われますが、正しくはプラットフォーム(基盤となる仕組み)の名前です。
そして、その中で使われる通貨が「イーサ(ETH)」です。
たとえば、アプリを動かすときや取引を行うときには、手数料としてイーサ(ETH)が必要になります。
この仕組みがあることで、ネットワークを安全に維持でき、世界中の人が公平にサービスを利用できるようになっています。
初心者が混乱しやすいポイントは「イーサリアム=通貨」だと思ってしまうことです。正しくは
- イーサリアム=仕組み・基盤
- イーサ=その中で使うお金
と整理して覚えると、理解しやすいでしょう。
ビットコインは「価値の保存」イーサリアムは「サービスの基盤」
ビットコインとイーサリアムはどちらも仮想通貨ですが、その役割は大きく異なります。ビットコインは「デジタルゴールド」と呼ばれ、価値を保存することに特化した存在です。金(ゴールド)のように、長期的に価値を保有する手段として注目されています。
一方、イーサリアムは「価値の保存」よりも「サービスの基盤」としての役割が大きいです。
スマートコントラクトを使ってアプリやサービスを動かせるため、DeFiやNFT、ブロックチェーンゲームなど多様な分野で利用されています。
初心者が理解しておくべきなのは
- ビットコイン=貯めるもの
- イーサリアム=使ってサービスを動かすもの
というシンプルな違いです。この視点をもつと、それぞれの位置づけが分かりやすくなるでしょう。

イーサリアムの3つのメリット
イーサリアムには、ビットコインにはない独自の強みがあります。初心者が知っておくべき代表的なメリットは、次の3つです。
- 契約や取引を自動で実行できる「スマートコントラクト」が組み込まれている
- さまざまなアプリケーションを開発できる
- 新しいトークン(独自のコイン)を発行できる
これらの特徴があるからこそ、イーサリアムは仮想通貨としてだけでなく、金融やアート、ゲームなど幅広い分野で活用されているのです。
それぞれのメリットについて、初心者でも分かるように解説していきます。
契約や取引を自動で実行できる「スマートコントラクト」がある
イーサリアム最大の特徴は「スマートコントラクト」と呼ばれる仕組みが組み込まれていることです。
| 【スマートコントラクト】 あらかじめプログラムされた条件が満たされると、自動的に契約や取引が実行される仕組み |
たとえば「AさんがBさんにお金を支払ったら、自動でデジタルアートの所有権が移る」といった取引を、人を介さずに実現できます。
従来の契約では、仲介業者や信頼できる第三者が必要でした。しかしスマートコントラクトを使えば、ブロックチェーン上で誰でも同じルールを確認できるため、不正や改ざんのリスクを大幅に減らせます。
重要なのは「人の手を介さず、プログラム通りに契約が進むから安心感がある」という点です。
これにより、NFTの売買やDeFi(分散型金融)といった新しいサービスが実現可能になっています。
NFTやDeFiなど多様なアプリを開発・利用できる
イーサリアムは「分散型アプリケーション(DApps)」を作れるプラットフォームとして、多くの開発者に利用されています。
| 【DApps】 特定の会社や管理者に依存せず、ブロックチェーン上で動作するアプリ |
たとえば
- DeFi:銀行のようにお金を預けたり借りたりできる
- NFTマーケット:デジタルアートやアイテムを売買できる
などがその代表例です。
これらは、スマートコントラクトを基盤にして動いており、利用者は誰でも安全に使える仕組みになっています。
だからこそ、多くの企業や開発者が注目し続けているのです。

誰でも新しいトークンを発行できる
イーサリアムの仕組みを使うと、誰でも独自のトークン(仮想通貨のようなデジタル資産)を作ることができます。
これは「ERC-20」や「ERC-721」といったルール(規格)に従って発行され、世界中の取引所やアプリで使えるようになります。
たとえば
- プロジェクトごとに資金を集めるためのトークン
- NFT(デジタルアートやアイテムを証明するトークン)
などもこの仕組みで作られています。特別な設備や銀行の承認がなくても、誰でも新しい価値を発行できる点は、イーサリアムの大きな強みです。
イーサリアムは新しい通貨やデジタル資産を生み出すための土台でもあるため、ビジネスや投資の分野で広く活用されています。
イーサリアムのデメリット3選

イーサリアムには大きな可能性がある一方で、初心者が注意すべきデメリットも存在します。
代表的なものは、次の3つです。
- 取引処理が遅く、利用者が増えると混雑しやすい
- ガス代(手数料)が高く、少額取引だと負担が大きい
- 発行上限がなく、EIP-1559により取引手数料の一部がバーンされる仕組みが導入され、実際には供給量が抑制される傾向があります。
つまり、イーサリアムは便利な仕組みをもっていますが、速度・コスト・希少性といった面で弱点が残っているということです。
イーサリアムを理解するうえで、この3つの課題を知っておくことは欠かせません。それぞれの内容を詳しく見ていきましょう。
取引処理が遅くスケーラビリティに課題がある
イーサリアムは多くのサービスに利用されていますが、その分だけ取引の処理速度に課題があります。
ビットコインよりは速いものの、1秒間に処理できる件数(トランザクション数)は限られています。
そのため、利用者が急増すると取引が詰まりやすくなるのです。
これを「スケーラビリティ問題」と呼び、送金や契約の実行が遅れる原因となっています。
特に、NFTの売買やDeFiで一時的に取引が集中すると、処理待ちが発生してストレスを感じることがあります。
こうした問題はすでに技術的に認識されており、開発チームも改善に取り組んでいます。ただし、現時点では「利用が集中すると遅れる可能性がある」と理解しておくことが重要です。
ガス代(手数料)が高くコストがかかる
イーサリアムで取引やアプリを利用するときには「ガス代」と呼ばれる手数料が必要です。
これは取引を処理する人(マイナーやバリデーター)に支払う対価ですが、需要が高まると料金が跳ね上がる仕組みになっています。
そのため、少額の送金やNFTの購入でも、手数料のほうが高くついてしまうケースも少なくありません。
たとえば、数百円の取引をしたいだけなのに、同じくらいかそれ以上のガス代を払うことになる場合もあります。
これは初心者にとって大きなハードルであり「せっかくの便利な仕組みなのに使いにくい」と感じる原因になっています。
今後のアップデートによって改善が期待されていますが、現状では「イーサリアムを使うにはコストがかかる」という点を理解しておくことが大切です。
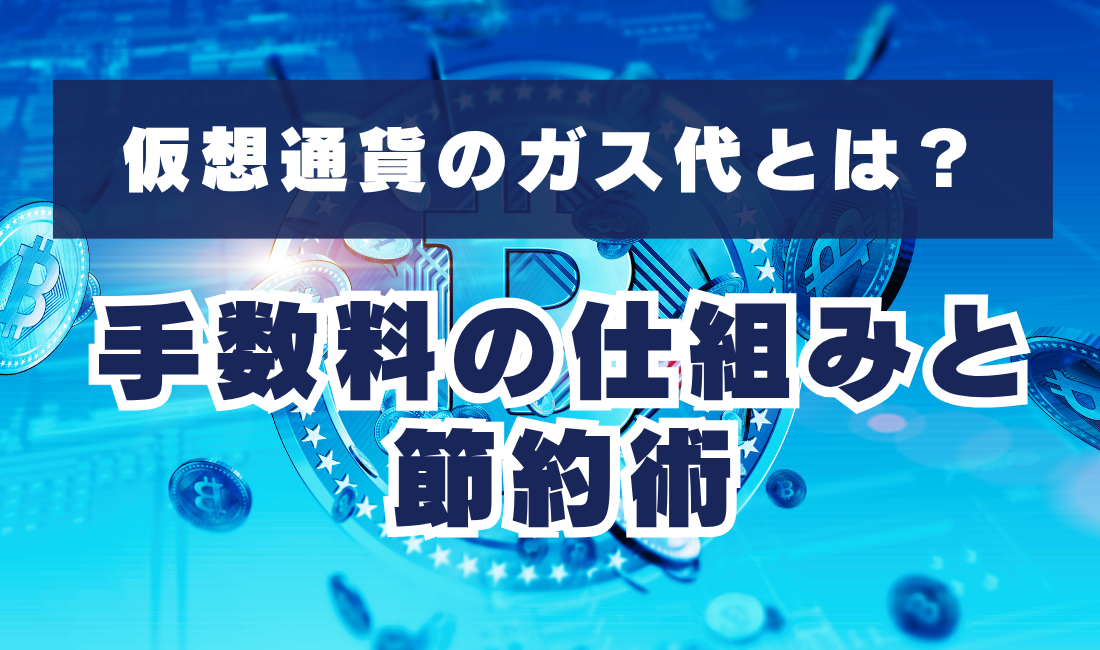
発行上限がなく価値の希少性が下がる可能性がある
ビットコインには「最大2100万枚」という発行上限がありますが、イーサリアムにはそのような明確な上限がありません。
つまり、理論上は今後も新しいイーサ(ETH)が発行され続ける仕組みになっています。
この特徴は「将来の希少性が下がるのでは?」という懸念につながります。投資の世界では、供給が限られているものほど価値が保たれやすいからです。
ただし近年は、取引手数料の一部がバーン(消滅)される仕組みが導入され、流通量を一定に抑える工夫も進められています。
そのため「無限に増えるから必ず価値が下がる」という単純な話ではありません。
価格の動きを判断する際には、仕組みの違いをしっかり押さえておく必要があります。
イーサリアムの将来性が期待されている2つの理由
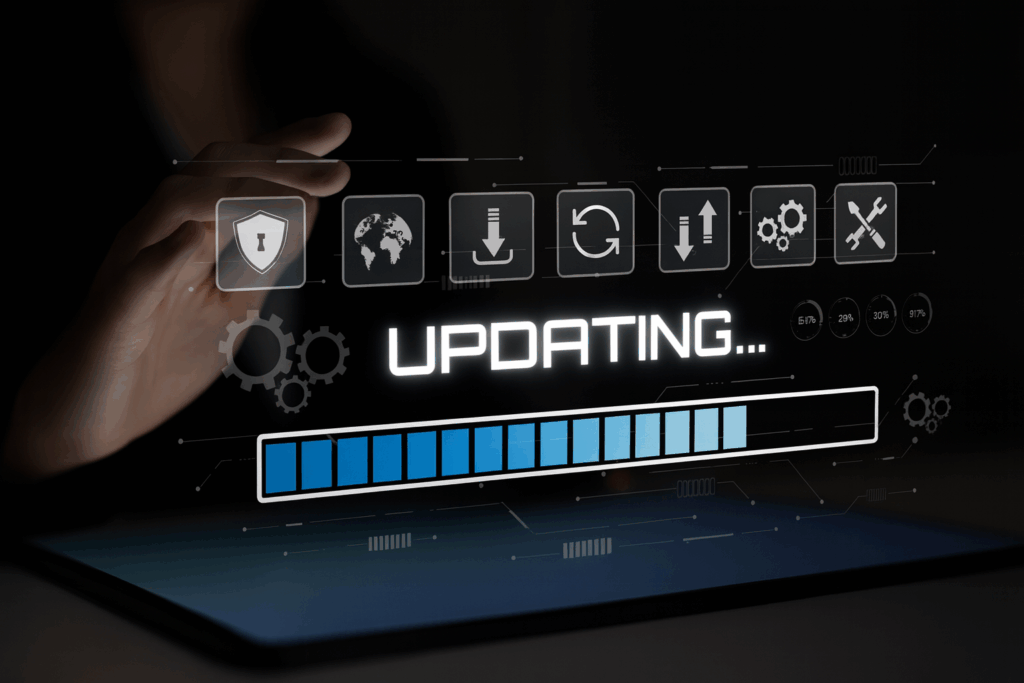
イーサリアムは、ビットコインと並んで世界的に注目されている仮想通貨です。その理由は、単に「通貨」として使えるだけでなく「アプリやサービスの基盤」として幅広く活用できる仕組みをもっているからです。
特に注目されているのは、以下の2点です。
- NFTやDeFiの拡大によって、利用がさらに広がる可能性がある
- アップデートにより、処理速度や手数料の課題が改善される見込みがある
つまり、現時点で抱えているデメリットが将来的に解決され、さらに多くの分野で使われていく可能性があるのです。
こうした「課題」と「成長の期待」を両方理解しておくことが重要です。
NFTやDeFiの拡大で利用がさらに広がる可能性がある
イーサリアムが注目される大きな理由のひとつが、NFTやDeFiの基盤として広く利用されている点です。
| 【NFT】 アートや音楽、ゲーム内アイテムなどのデジタル資産を「唯一無二のもの」として証明できる仕組みで、2021年以降世界的なブームになった。 NFTの多くはイーサリアムのブロックチェーン上で発行・取引されている。 |
| 【DeFi】 銀行のような仲介を介さずに、仮想通貨の貸し借りや交換、利息運用を行えるサービスの総称。 従来の金融サービスに代わる選択肢として注目を集め、利用者は年々増加している。 |
NFTやDeFiは、すでに大きな市場規模をもっています。しかし、今後さらに利用シーンが拡大することで、イーサリアムの需要も一層高まると期待されています。
アップデートによって速度や手数料の課題解決が期待でき
イーサリアムは便利な一方で「処理速度が遅い」「ガス代が高い」という課題を抱えています。
しかし、開発チームはこれを放置しているわけではなく、継続的なアップデートを進めています。
すでに「プルーフ・オブ・ステーク(PoS)」という新しい仕組みへの移行が完了し、消費電力を大幅に削減することに成功しました。
| 【プルーフ・オブ・ステーク(PoS)】 仮想通貨を多く保有している人が取引の承認役になり、その報酬を得られる仕組み |
今後は「シャーディング」と呼ばれる技術によって、複数の処理を同時並行で行えるようにするなど、スケーラビリティ(拡張性)の改善が期待されています。
つまり、現在のイーサリアムが抱える弱点も将来的には解決に近づく可能性が高いのです。
この「進化し続ける仕組み」こそが、長期的な成長を見込める理由のひとつといえるでしょう。
初心者がイーサリアムを扱うときの3原則

イーサリアムは将来性のある仮想通貨として注目されていますが、初心者が安心して扱うためにはいくつかの注意点があります。
特に大切なのは、次の3つです。
- 必ず国内取引所で購入して安全に始める
- 大金を入れず少額から体験して慣れる
- ステーキングは利回りがあるがリスクも伴う
これらを意識することで、大きな損失を防ぎながら、イーサリアムの仕組みや活用方法を安心して学ぶことができます。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
必ず国内取引所で購入して安全に始める
初心者がイーサリアムを購入する際は、必ず国内の仮想通貨取引所を利用するのが安心です。
国内取引所であれば金融庁の登録を受けており、セキュリティ体制や利用者保護の仕組みが整っています。
万が一トラブルがあっても、日本語でサポートを受けられるため安心感があります。
一方で、海外取引所は規制が緩くサポートも十分ではないため、トラブル時に資金を取り戻せないリスクが大きいのが現実です。
初心者が最初から海外取引所に挑戦するのは、危険だといえるでしょう。
まずは国内取引所でイーサリアムを安全に購入し、慣れてから次のステップを検討するのが最も安心な始め方です。
<h3>大金を入れず少額から体験して慣れる</h3>
イーサリアムは価格の変動が大きく、短期間で数十%以上の値動きが起きることも珍しくありません。
そのため、初心者がいきなり大金を投じてしまうと、急落によって大きな損失を抱え、精神的にも大きな負担となってしまいます。
最初は「失っても生活に影響のない範囲」の少額で始めるのがおすすめです。1万円程度でも実際に取引を体験すれば、チャートの動きや価格の変動のスピードを肌で感じられます。
少額なら損失が出ても「勉強代」と割り切りやすく、安心して学びにつなげられるでしょう。
投資に慣れてきたら、自分のリスク許容度を踏まえて投資額を調整するのが健全なステップアップの方法です。
ステーキングは利回りがあるがリスクも伴う
イーサリアムには「ステーキング」という仕組みがあり、保有しているETH(イーサ)を一定期間預けることで利回りを得られる可能性があります。
| ステーキング:保有している仮想通貨を一定期間預けると、報酬を得られる |
このステーキングは銀行預金の利息のように資産が増えるため、魅力的に感じる人も多いでしょう。
しかし、ステーキングにはリスクも存在します。まず、預けた期間中はすぐに引き出せないケースがあり、価格が急落しても売れない可能性があります。
また、利用するサービスによっては運営リスク(ハッキングや倒産)もあり、預けた資金が戻らないリスクもゼロではありません。
初心者にとっては「資産を増やす方法」というより「仕組みを学ぶ体験」として少額で試すのが安心です。
メリットとリスクを正しく理解したうえで、利用することが重要です。
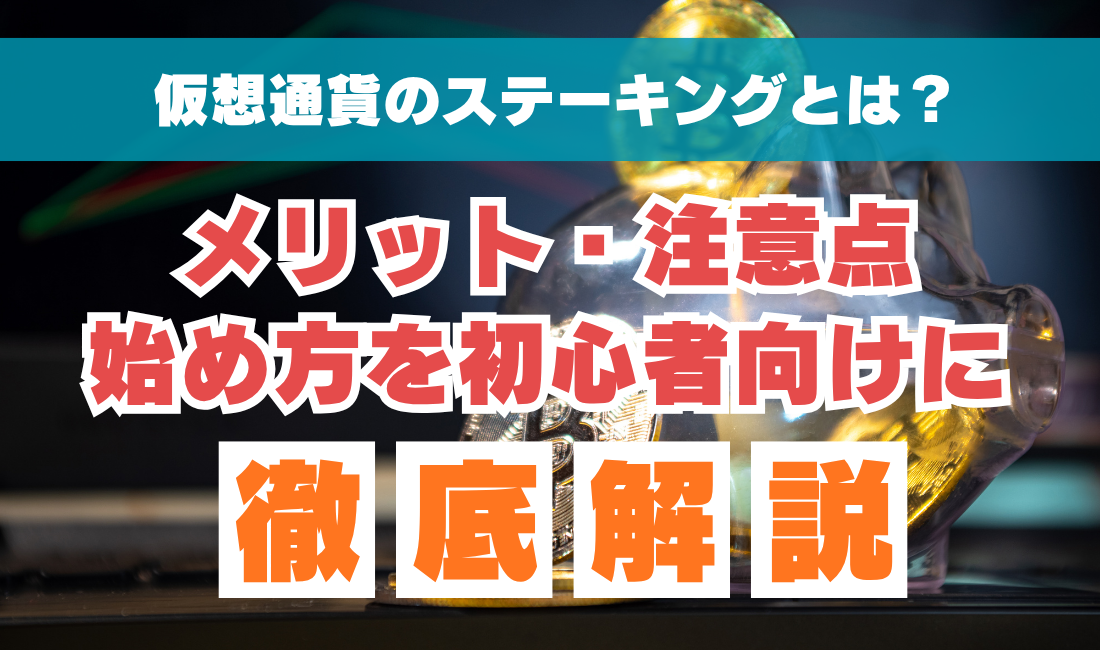
まとめ:イーサリアムは仕組みを理解し少額から体験するのが安心

イーサリアムは、ビットコインとは異なり「アプリを動かせるブロックチェーン」として幅広いサービスを支える存在です。
NFTやDeFiといった分野で利用が拡大し、将来性も注目されています。しかし同時に「取引の遅さやガス代の高さ」「発行上限がないことによる希少性の課題」など、デメリットも存在します。
初心者にとって重要なのは「夢や話題性」だけに流されず、仕組みとリスクを理解したうえで触れることです。
特に投資を考える際は大金を入れるのではなく、少額から体験して慣れるのが安心です。
イーサリアムは資産形成のメインではなく「学びながら体験できる投資対象」として向き合うのが安全な方法だといえるでしょう。