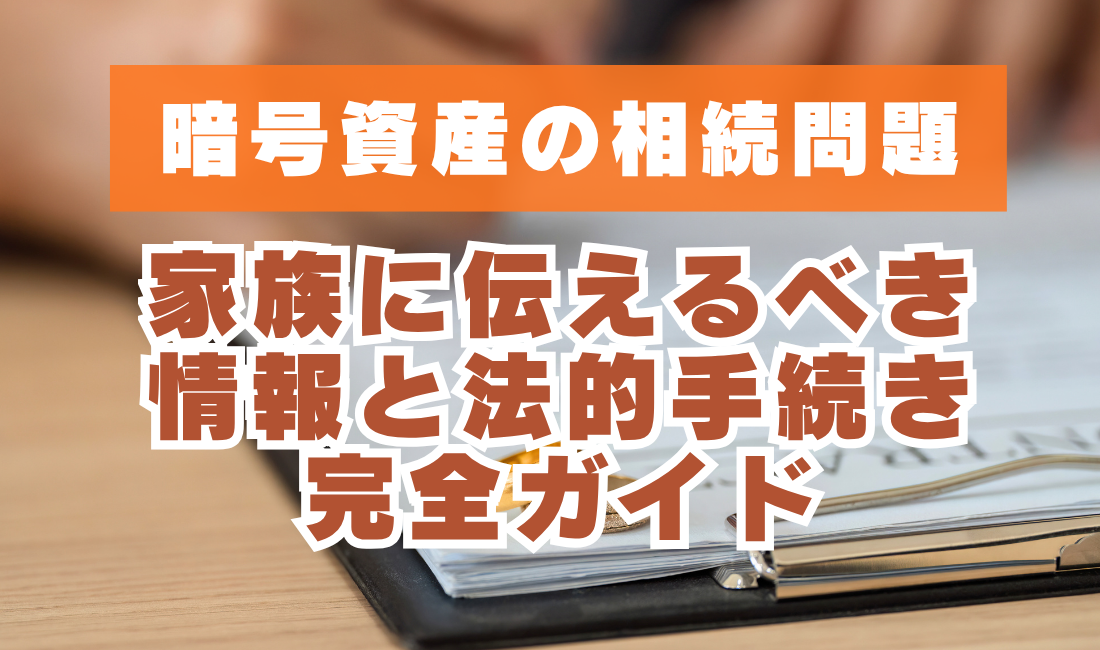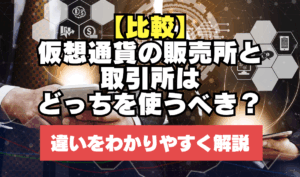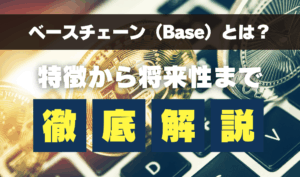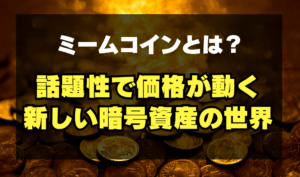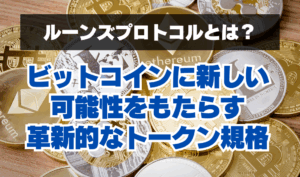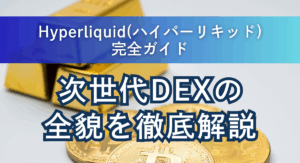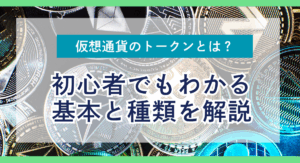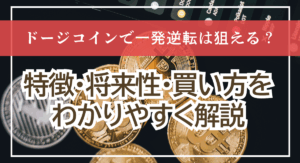仮想通貨(暗号資産)の普及に伴い、その相続問題が注目を集めています。ビットコインやNFTといったデジタル資産は、秘密鍵やパスワードを知らなければ、家族であっても相続が困難になります。
本記事では、仮想通貨の相続における課題と対策、必要な情報管理や法的手続きについて、詳しく解説します。
1. 仮想通貨の相続が難しい理由

非中央集権型の特徴
仮想通貨は、銀行や証券会社のような中央集権的な機関を介さずに管理される非中央集権型の資産です。そのため、口座名義人が亡くなった場合でも、第三者が簡単にその資産を把握・管理することはできません。
管理は基本的に本人の秘密鍵に依存しており、その所在や管理方法を家族が知らない場合、相続人が資産を引き継ぐのは極めて困難になります。
また、仮想通貨は紙の証券や通帳のような形で物理的に残らないため、資産の存在自体に気づかれないケースも少なくありません。そのため、日頃から情報管理を徹底し、信頼できる家族と共有しておくことが非常に重要です。
パスワードの喪失リスク
仮想通貨のウォレットは、ログイン情報や復元用フレーズ(シードフレーズ)によって管理されています。これらを相続人が把握していない場合、資産にアクセスする術がなくなり、事実上回収不可能になる可能性があります。
銀行口座や不動産と異なり、正式な相続手続きを踏んでもアクセスができないというのが仮想通貨特有の問題です。
アクセス情報を適切に管理しないと、相続資産としての価値があっても、実際には取り出す手段を完全に失ってしまう恐れがあるので注意が必要です。
2. 相続対象となる暗号資産の種類と確認方法

相続対象となる暗号資産には、以下のような種類があります。
- ビットコイン(BTC)やイーサリアム(ETH)などの主要な仮想通貨
- DeFi(分散型金融)で運用されているトークン
- 中央集権型取引所(CEX)に預けられている資産
- ハードウェアウォレットやソフトウェアウォレットに保管されている資産
- NFT(非代替性トークン)
これらの資産を確認するには、まず被相続人が利用していた取引所の履歴やメールアカウントの受信履歴を確認し、取引所から送信されるメールや資産残高通知、認証アプリなどの痕跡を確認する必要があります。ウォレットアドレスが判明すれば、ブロックチェーン上で公開情報として資産状況を追跡することも可能です。
また、NFTやDeFi関連資産は、従来の取引履歴では確認しきれない場合があるため、ブロックチェーンエクスプローラーや、ポートフォリオ管理サービスを活用することで、保有資産の全容を把握しやすくなります。
特にDeFiでは、貸付け、ステーキング報酬や担保の動きが自動化されているため、スマートコントラクトの仕組みも理解しておくことが望ましいです。
相続人や代理人は、まず資産の存在を突き止め、次にアクセス手段を確保し、必要に応じて専門家の支援を受けることで、適切な評価・引き継ぎを進めることができます。
3. 家族に伝えておくべき情報とは?
仮想通貨を確実に相続してもらうためには、生前に必要な情報を整理し、家族に伝えておくことが不可欠です。以下の項目は、特に整理しておきましょう。
- 保有銘柄の一覧(ビットコイン、イーサリアム、その他のアルトコインなど)
- 保管場所の明示(取引所、ハードウェアウォレット、モバイルウォレットなど)
- アクセス情報(ログインID、パスワード、秘密鍵、シードフレーズなど)
これらの情報は、定期的に更新して安全な場所に保管し、信頼できる家族に伝えるか、書面で残す方法が推奨されます。
セキュリティ上の観点から、すべてをデジタルで管理するよりも、手書きで保管する方法が有効なケースもあります。
また、万が一に備えて情報の保管場所や管理方法についても明確にしておくことが大切です。具体的には、アクセス情報は紙に記載して封筒に保管し、遺言書や公正証書とともに信頼できる保管場所に置いておくと、万一の際にもスムーズに対応できます。
また、仮想通貨に関する知識が乏しい家族のために、基本的な操作手順や注意点を簡潔にまとめたガイドを添えると、相続後の対応がよりスムーズになります。
仮想通貨の特性を理解し、適切な情報伝達と記録を行うことが、安心して資産を引き継ぐための第一歩です。
4. 相続のために必要な法的手続きの流れ

仮想通貨も、法律上は他の金融資産や不動産と同様に「相続財産」として扱われます。被相続人が保有していた仮想通貨は、正当な法的手続きを踏むことで、相続人に引き継がれる対象となります。
ただし、仮想通貨特有の性質から、その手続きには従来の資産以上の注意や準備が求められます。ここでは、具体的な流れについて詳しく解説します。
遺言書の準備
まず、相続トラブルを未然に防ぐために、生前のうちに有効な遺言書を作成することが非常に重要です。仮想通貨に関しては、紙の通帳や目に見える資産と異なり、保有者本人しか存在を把握していないことも多く、遺言書に明記されていなければ、相続人がその存在にすら気づけない可能性があります。
相続人の確認
相続の手続きを進める上では、まず誰が法定相続人となるかを確定する必要があります。通常は、戸籍謄本や住民票を取得し、配偶者や子ども、親、兄弟姉妹といった相続権を持つ人物を法的に確認します。
この作業は仮想通貨に限らず、すべての遺産に共通する重要なステップです。
税務申告の注意点
仮想通貨は、相続時に相続税の課税対象となります。相続税の課税額を算出するためには、被相続人が死亡した日時点での仮想通貨の市場価値を正確に評価する必要があります。
国内外の複数の取引所に上場している銘柄の場合、平均価格を算出する方法や、特定の取引所の価格を基準とする方法など、評価方法は一定のルールに基づいて行われます。
また、仮想通貨がDeFiで運用されていたり、NFTなどの形で保有されている場合は、その評価が複雑になるため、最新の税務ガイドラインを踏まえたプロのサポートを検討するのも良い方法です。
5. 相続対策として今できること

エンディングノートの活用
エンディングノートには、自身の保有資産や取引履歴、保管方法、アクセス情報、仮想通貨の種類や使用している取引所・ウォレットの一覧などを詳しく記載しておくことが重要です。
※エンディングノートは法的効力がない為、注意が必要です。
これにより、家族や相続人が資産の全体像を正しく把握しやすくなります。法的な効力はないものの、相続手続きをスムーズに進めるための補助資料として大きな役割を果たします。
専門業者への相談
仮想通貨の相続は専門的な知識を要するため、仮想通貨に精通した税理士、弁護士、または信託会社への相談が非常に有効です。
こうした専門家は、資産の適切な評価、税務面での対策、遺言書作成の法的サポートまで多面的な支援を行ってくれます。
特に、海外取引所の利用やDeFi資産が含まれる場合、経験豊富な専門家の助言が役立ちます。
暗号資産用遺言の作成
仮想通貨を円滑に相続してもらうためには、通常の遺言書に加えて、暗号資産に特化した「暗号資産用遺言」を作成する方法も効果的です。
具体的には、秘密鍵やシードフレーズの管理方法、アクセス手順、資産の保管場所、認証手段などを詳細に記載し、相続人が安全かつ迅速に資産へアクセスできるよう備えておきます。また、信頼できる第三者に内容を預ける体制を整えておくと、さらに安心です。
6. まとめ:家族を困らせない、資産継承の準備とは
仮想通貨の相続は、一般的な資産と比べて情報管理と技術的知識が求められる点で特有の難しさがあります。
銀行口座や不動産のように第三者の関与によって相続が進められる資産とは異なり、仮想通貨は秘密鍵やパスワードを本人しか知らない場合が多く、それらが失われれば、法的手続きを経ても資産にアクセスできないというリスクがあります。
特に、ブロックチェーン技術の匿名性と不可逆性がこの問題をさらに複雑にしています。そのため、生前の備えが極めて重要となります。
家族に伝えておくべき情報を丁寧に整理し、遺言書やエンディングノートを活用することが推奨されます。また、税理士や弁護士といった専門家から法的・税務的なアドバイスを受けることで、相続手続きを円滑に進めるだけでなく、不要なトラブルを回避することにもつながります。
自分自身と家族の未来を守るためにも、仮想通貨特有のリスクに備えた対策を、できるだけ早い段階から講じておくことが大切です。