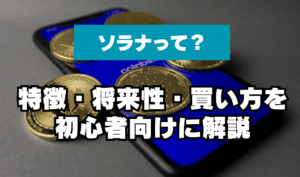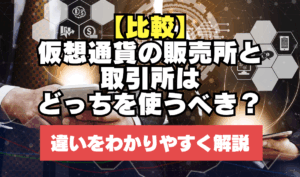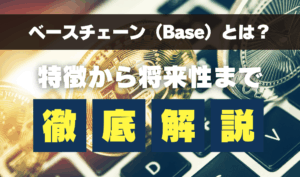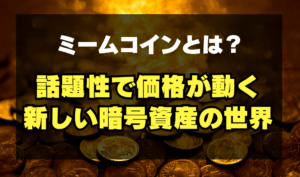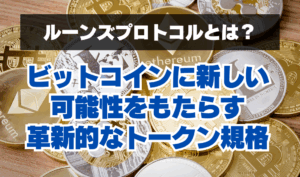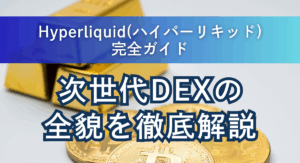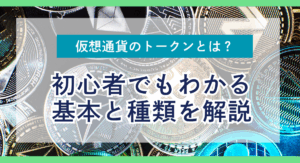近年、ブロックチェーン技術を活用した新しい金融商品として「セキュリティトークン」が注目を集めています。
従来の証券とは異なる特徴を持ち、投資の世界に革新をもたらす可能性があるとして、世界中の金融機関や投資家から熱い視線が注がれています。
しかし、「セキュリティトークンって一体なに?」「暗号資産とどう違うの?」といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
本記事では、セキュリティトークンの基本的な仕組みから特徴、メリット・デメリット、そして将来性まで、初心者の方にも分かりやすく解説していきます。
セキュリティトークンとは

セキュリティトークンとは、株式や債券、不動産などの伝統的な有価証券をブロックチェーン技術によってデジタル化したものです。
英語では「Security Token」と表記され、日本語では「デジタル証券」や「トークン化証券」とも呼ばれています。
従来の証券は紙の証券や電子記録として管理されてきましたが、セキュリティトークンはブロックチェーン上で発行・管理されることで、より効率的で透明性の高い取引が可能です。
暗号資産(仮想通貨)との違い
セキュリティトークンと暗号資産は、どちらもブロックチェーン技術を活用していますが、その性質は大きく異なります。
ビットコインは決済や価値保存を目的とした“ペイメントトークン”、イーサリアムなどはサービス利用権を伴う“ユーティリティトークン”に分類されます。
これらは基本的に、投資契約に基づく権利を表すものではありません。
一方、セキュリティトークンは、発行体の資産や収益に対する権利、配当を受け取る権利、議決権など、証券としての法的権利を表します。
つまり、実物資産や企業の株式などの裏付けがあり、金融商品取引法などの証券関連法規の規制対象となる点が最大の違いです。
ブロックチェーン技術の活用
セキュリティトークンの基盤となるブロックチェーン技術は分散型台帳技術とも呼ばれ、取引記録を複数のコンピュータで共有・管理する仕組みです。
この技術により、取引の透明性が確保され、改ざんが極めて困難になります。
また、スマートコントラクトを活用することで、将来的には配当の自動分配や取引条件の自動確認といった業務の自動化も可能になると期待されています。
そのため、従来の証券取引で必要だった多くの仲介者や煩雑な手続きを省略できるのです。
セキュリティトークンの特徴

セキュリティトークンには、従来の証券にはない独自の特徴があります。
ここでは、その主な特徴について詳しく見ていきましょう。
- 安全性の向上
- 機能の追加
- 24時間365日取引可能
- 取引記録の透明性
安全性の向上
セキュリティトークンの最も重要な特徴は、証券関連法規の規制対象となることです。
つまり、日本では金融商品取引法、アメリカではSEC(証券取引委員会)の規制下に置かれます。
これは一見デメリットのように思えるかもしれませんが、実は投資家保護の観点から非常に重要です。
なぜなら、発行体は厳格な情報開示義務を負い、不正行為には法的制裁が科されるからです。
この点で、規制の曖昧な暗号資産よりも安全性が高いと言えるでしょう。
機能の追加
セキュリティトークンは、スマートコントラクトによってさまざまな機能をプログラムできます。
例えば、配当金の自動分配、保有者の国籍や資格の自動確認、取引制限の実装などが可能です。
従来の証券では、こうした処理には人手による確認や複雑な事務手続きが必要でしたが、セキュリティトークンではコードによって自動的に実行されます。
これにより、ヒューマンエラーのリスクが減少し、運用コストも大幅に削減できるでしょう。
取引記録の透明性
ブロックチェーンの特性により、すべての取引履歴が記録され、誰でも確認できます(プライバシーに配慮した設計も可能)。
そのため、不正取引や市場操作の防止につながり、市場全体の信頼性が向上します。
また、保有者情報の正確な把握が容易になるため、配当の支払いや株主総会の運営などもスムーズに行え、投資家の満足度が高まるでしょう。
セキュリティトークンのメリット

セキュリティトークンは、投資家、発行体、金融機関のそれぞれにとって多くのメリットをもたらします。
- コスト削減の実現
- 価値の部分保有
- 24時間365日取引可能
コスト削減の実現
証券の発行・管理・取引には、従来多くの仲介者が関与していました。
例えば、証券会社・信託銀行・名義書換代理人などが挙げられ、各段階で手数料が発生します。
しかしセキュリティトークンでは、ブロックチェーンとスマートコントラクトにより、これらの仲介者を減らせます。
発行コスト・管理コスト・取引コストのすべてが削減され、その恩恵は投資家と発行体の双方に及ぶでしょう。
価値の部分保有
不動産や美術品など、従来は高額で購入が困難だった資産も、セキュリティトークン化することで小口化が可能になります。
例えば、10億円の不動産を1万分割してトークン化すれば、1口10万円から投資できるようになります。
この特徴により、これまで富裕層しかアクセスできなかった投資機会が、一般の投資家にも開かれることになるでしょう。
また、発行体にとっても、より多くの投資家から資金を調達できる機会が生まれます。
24時間365日取引可能
従来の証券取引所は、平日の限られた時間しか開いていません。
しかし、ブロックチェーン上で管理されるセキュリティトークンは、理論上24時間365日の取引が可能ですが、現行制度では取引所の運営時間に制約を受けます。
これにより、投資家は自分のライフスタイルに合わせた柔軟な投資活動ができるようになります。
また、グローバルな時間帯の違いを気にせず、世界中の投資家とリアルタイムで取引できる可能性も広がるでしょう。
セキュリティトークンのデメリット

多くのメリットがある一方で、セキュリティトークンにはいくつかの課題やデメリットも存在します。
- セキュリティリスク
- 相互運用性の課題
セキュリティリスク
ブロックチェーン自体は堅牢な技術ですが、それを取り巻くシステムには脆弱性が存在する可能性があります。
取引プラットフォームのハッキング、スマートコントラクトのバグ、詐欺的なプロジェクトなど、さまざまなリスクが考えられます。
特にスマートコントラクトは一度デプロイすると修正が困難なため、設計段階での十分な検証が不可欠です。
過去には、スマートコントラクトの脆弱性を突かれて多額の資金が流出した事例もあります。
セキュリティトークンを扱う際は、上記のようなセキュリティリスクを念頭においておきましょう。
相互運用性の課題
現在、さまざまなブロックチェーンプラットフォームでセキュリティトークンが発行されていますが、異なるプラットフォーム間での互換性が低いという問題があります。
そのため、投資家は複数のウォレットやプラットフォームを使い分ける必要が生じ、利便性が低下します。
業界全体での標準化が進んでいますが、完全な相互運用性の実現にはまだ時間がかかりそうです。
元々ブロックチェーン技術やスマートコントラクトは、一般の投資家にとって理解が難しい面があるので、複数ウォレットの管理は投資家の参入ハードルを上げてしまうリスクがあります。
セキュリティトークンの将来性

課題はあるものの、セキュリティトークンの将来性は非常に明るいと考えられています。
例えばボストンコンサルティンググループの試算では、2030年までにトークン化された資産の市場規模が16兆ドルに達する可能性があると示しているなど、多くの調査機関がセキュリティトークン市場の急成長を予測しています。
特に期待されているのが、不動産のトークン化です。
世界の不動産市場は数百兆円規模ともいわれ、そのごく一部でもトークン化されれば巨大な市場が生まれます。
すでに日本ではSBI証券や野村ホールディングスなどが不動産STOを実施しており、実用化はすでに始まっています。
不動産投資の敷居が下がることで、個人投資家の裾野が大きく広がる可能性があるでしょう。
また不動産以外にも、アート作品、知的財産権、スポーツ選手の将来収益権、再生可能エネルギー設備など、様々な資産がトークン化の対象となっています。
これまで証券化が難しかった資産も、セキュリティトークンによって投資対象となり、新しい投資機会が次々と生まれることが期待されます。
このように、セキュリティトークンは多くの分野での利用が可能です。
まとめ|セキュリティトークンは新たな金融インフラになる可能性がある
セキュリティトークンはブロックチェーン技術を活用して、伝統的な証券をデジタル化した新しい金融商品です。
暗号資産とは異なり、実物資産の裏付けがあり、証券関連法規の規制対象となることが特徴です。
セキュリティトークンは、まだ発展途上の技術ですが、今後数年で大きく成長することが予想されます。
投資家にとっては新しい投資機会を、企業にとっては効率的な資金調達手段を提供する、次世代の金融インフラとなる日も近いかもしれません。
これから投資を検討される方は、技術の進展や規制動向を注視しながら、十分な知識を身につけた上で、慎重に判断することが大切です。
セキュリティトークンは、私たちの投資の未来を大きく変える可能性を秘めた、注目すべき技術と言えるでしょう。