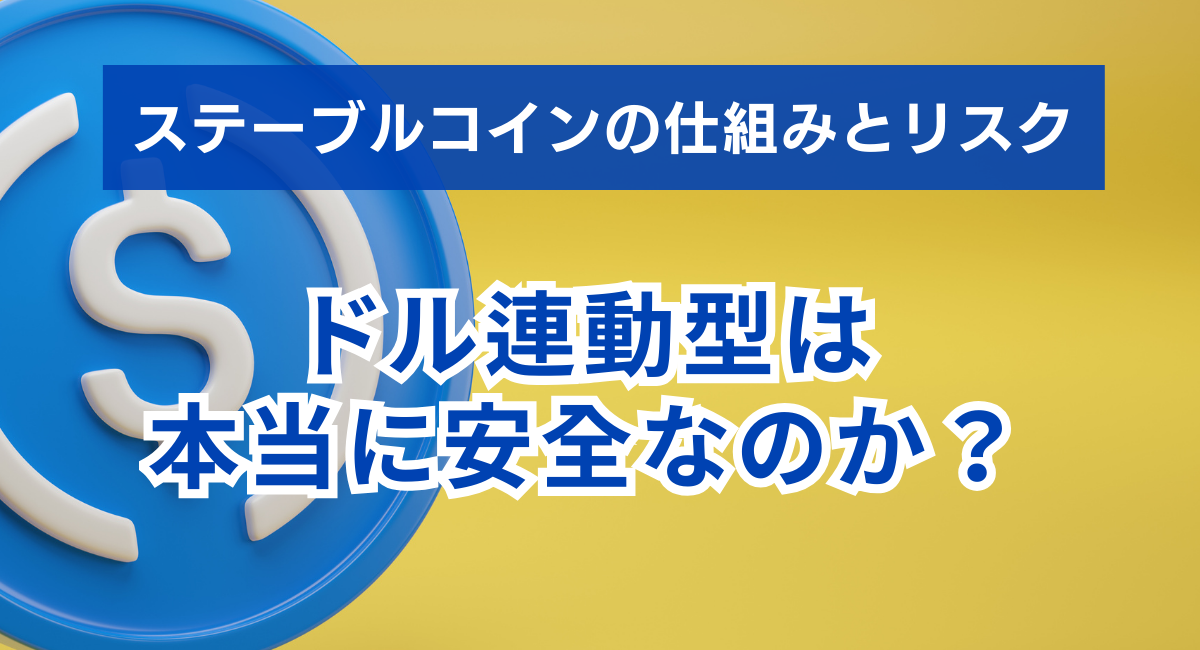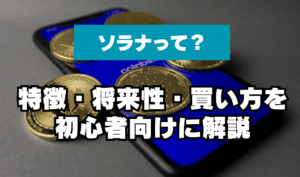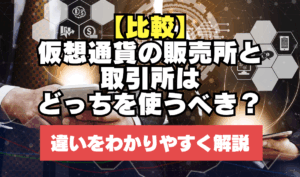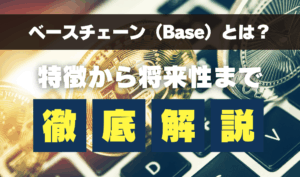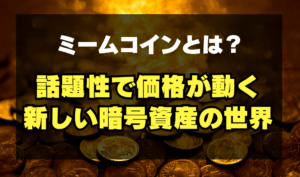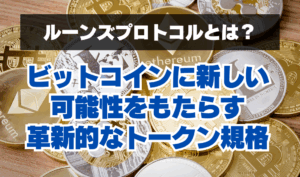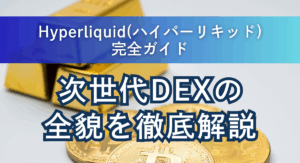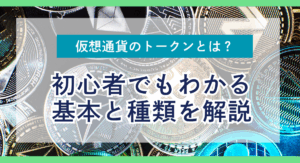暗号資産市場において価格の安定性を保つ「ステーブルコイン」は、近年急速に注目を集めています。
2025年現在、ステーブルコインの市場規模は2,510億ドルを超え、デジタル決済の新たな基盤として期待されています。
特に米国では第二次トランプ政権によりステーブルコインが盛り上がりを見せており、日本でも2025年8月にJPYCは円建てステーブルコインとして注目されており、法制度の整備が進む中で承認が期待されています。
しかし、ステーブルコインは本当に「安定」なのでしょうか。
価格変動リスクを抑えた設計であっても、発行者の信頼性や担保資産の透明性など、さまざまなリスクが潜んでいます。
本記事では、ステーブルコインの基本的な仕組みから各種類の特徴、そして投資家が知っておくべきメリット・デメリットを解説するので、ぜひ最後までご覧ください。
ステーブルコインとは?

ステーブルコインとは、米ドル等の法定通貨やコモディティ(商品)など、特定の資産価格と連動することを目的に設計された暗号資産の一種です。
従来のビットコインやイーサリアムといった暗号資産の最大の問題点は、価格変動の激しさでした。
日常的な決済手段として利用するには価値の安定性が不可欠であり、ステーブルコインはこの問題を解決するために開発されました。
2020年初頭のステーブルコイン市場の時価総額は1兆円以下でしたが、2022年12月には20兆円を超えており、ステーブルコイン市場が急速な発展を遂げてきたことが分かります。
ステーブルコインは3種類に分類される

ステーブルコインは、価値を安定させる仕組みによって大きく3つの種類に分類されます。
それぞれ異なるメカニズムと特徴を持っており、リスクの性質も大きく異なるため、以下で確認していきましょう。
- 法定通貨担保型
- 仮想通貨担保型
- アルゴリズム型
法定通貨担保型
法定通貨担保型ステーブルコインは、現在最も普及している形式です。
発行者が法定通貨(米ドルなど)や短期国債などの安定資産を担保として保有し、その裏付けのもとでステーブルコインを発行します。
代表的な法定通貨担保型ステーブルコイン
- USDT(テザー)
- USDC(USDコイン)
- EURC(サークル社発行のユーロ連動型)
法定通貨担保型ステーブルコインのメリットは、価格安定性が優秀で流動性が豊富な点です。
一方で、コインの発行母体があるため中央集権的な管理体制であったり、担保資産の透明性に課題があったりなどの注意点があります。
仮想通貨担保型
仮想通貨担保型ステーブルコインは、ビットコインやイーサリアムなどの暗号資産を担保として発行されます。
分散型の仕組みを採用することが多く、スマートコントラクトによって自動管理されるのが特徴です。
代表的な仮想通貨担保型ステーブルコイン
- DAI(MakerDAOプロトコル)
- sUSD(Synthetix)
通常は過担保となり、例えば1ドル相当のDAIを受け取るには、1ドル以上のイーサリアムを支払わなければならないという仕組みです。
仮想通貨担保型ステーブルコインの一番のメリットは、分散型で透明性が高い点です。
ただし、過担保が必要で資本効率が悪かったり、担保資産の価格変動リスクがあったりする点に注意が必要でしょう。
アルゴリズム型
アルゴリズム型ステーブルコインは、担保資産を持たず、アルゴリズムによる供給量調整で価格を安定させる試みです。
需要と供給のバランスをアルゴリズムで調整し、価格上昇時は供給量を増やして価格を下げ、価格下落時は供給量を減らして価格を上げます。
代表的なアルゴリズム型ステーブルコイン
- TerraUSD(UST)※2022年に破綻
- FRAX(部分的担保型とのハイブリッド)
理論的には最も資本効率の良い形式ですが、実用性には大きな課題があります。
例えば、2022年に発生したTerraUSD(UST)の破綻は、アルゴリズム型ステーブルコインの根本的な脆弱性を露呈させました。
そのため、現在は法定通貨担保型が市場の主流となっています。
主なステーブルコイン

現在市場で取引されている主要なステーブルコインについて、それぞれの特徴と最新動向を詳しく解説します。
- USDT
- USDC
- EURC
- JPYC
USDT
テザー(USDT)は、2014年にTether Limited社が発行した最初期のステーブルコインの一つで、現在も市場シェアの大部分(約65〜70%)を占めています。
Tether Limited社が発行し、米ドルとの1:1ペッグを維持しています。
| 発行者 | Tether Limited社 |
| 基準通貨 | 米ドル |
| 発行開始 | 2014年 |
| 時価総額 | 約1,500億ドル(2025年時点) |
USDTはステーブルコイン市場の最大手の通貨で、最も流動性が高く取引ペアが豊富です。
イーサリアムやトロンなど、多数のブロックチェーンで発行されています。
なおUSDTには懸念点もあり、長年にわたり担保資産の透明性に関する議論が続いているためTether社は定期的な監査報告を行っていますが、完全な透明性には課題があるとの指摘もあります。
USDC
USDコイン(USDC)は、Circle社とCoinbase社の共同プロジェクトとして2018年に開始されました。
2025年に入ってからは発行数が増加し、およそ25%を占めるまで成長しています。
| 発行者 | Circle社 |
| 基準通貨 | 米ドル |
| 発行開始 | 2018年 |
| 時価総額 | 約650億ドル(2025年時点) |
USDCは高い透明性があり、米国の規制に準拠した運営がされています。
Circle社はIPO計画を発表しており、規制適合性を強調していますが、実施状況には最新情報の確認が必要です。
このIPOで資金調達に成功したことにより、今後も規模を拡大していく可能性があるでしょう。
EURC
Euro Coin(EURC)は、Circle社が発行するユーロ連動型のステーブルコインで、米ドル以外の主要通貨との連動を目指したステーブルコインとして注目されています。
| 発行者 | Circle社 |
| 基準通貨 | ユーロ |
| 発行開始 | 2022年 |
| 時価総額 | 約2億ドル(2025年時点) |
ユーロ圏での決済用途が想定され1EURC=1ユーロに定められており、EU域内の規制要件に対応しています。
JPYC
JPYCは、2025年8月にJPYCが国内初の円建てステーブルコインとして金融庁承認を受けた、日本円連動型ステーブルコインです。
国内のデジタル決済革命の先駆けとして期待されています。
| 発行者 | Circle社 |
| 基準通貨 | 日本円 |
| 承認 | 2025年 |
| 流通開始 | 2025年秋予定 |
JPYCは1JPYC=1円のレートで設計されており、銀行預金や日本国債といった安全性の高い資産が価値の裏付けとして用いられます。
JPYCは2025年秋に流通開始予定で、企業間のB2B決済や個人間送金、DeFi分野での利用などが想定されています。
ステーブルコインのメリット・デメリット

ステーブルコインの導入を検討する際は、そのメリットとデメリットを正しく理解することが重要です。
- メリット
- デメリット
ステーブルコインのメリット
- 即時・低コストな国際送金
- 価格変動リスクの回避
従来の国際送金システム(SWIFT)では、送金完了まで数日を要し、高額な手数料が発生していました。
そして、現在の国際決済システム(例:SWIFT)は、遅い・高価・銀行の営業時間内にしか機能しないというデメリットがあります。
しかし、パブリックブロックチェーン上のステーブルコインは、24時間365日、ほぼ瞬時に、低コストで送金できる能力を秘めています。
また、ステーブルコインを利用することで、価格変動リスクも回避できるでしょう。
法定通貨などと連動して値動きするステーブルコインは価格安定性が高いため、決済資金などはステーブルコインに交換して保管しておくのがおすすめです。
ステーブルコインのデメリット
- 担保資産の透明性
- 利回りの制約
USDTなどの一部のステーブルコインでは、担保資産の詳細な内訳や保管状況が不透明な場合があります。
このような不透明性は、発行者の破綻や不正により、担保資産が毀損するリスクをはらんでいます。
また、価格安定性を重視するため、大きな投資リターンは期待できません。
そのため、仮想通貨で大きく稼ぎたいと考えている投資家には、ステーブルコインは適していないでしょう。
まとめ|ステーブルコインは仮想通貨市場に安定性をもたらす
ステーブルコインは、暗号資産の実用性を大幅に向上させる革新的な技術です。
2025年7月、米国ではステーブルコイン規制法案の審議が進められており、制度的基盤の整備が進行中です。
また、日本では2023年6月の改正資金決済法施行により「電子決済手段」として法制度が整備され、JPYCの承認により国内市場も本格始動しました。
ドル連動型ステーブルコインが「本当に安全」であるかは、発行者の信頼性、規制環境、技術的安定性など多くの要因に依存します。
完全にリスクフリーではありませんが、適切な理解と管理のもとで活用すれば、デジタル経済における重要な価値移転手段となるでしょう。
ステーブルコインは仮想通貨市場に安定性をもたらす重要なイノベーションとして、今後のデジタル社会インフラの中核を担うことが期待されます。