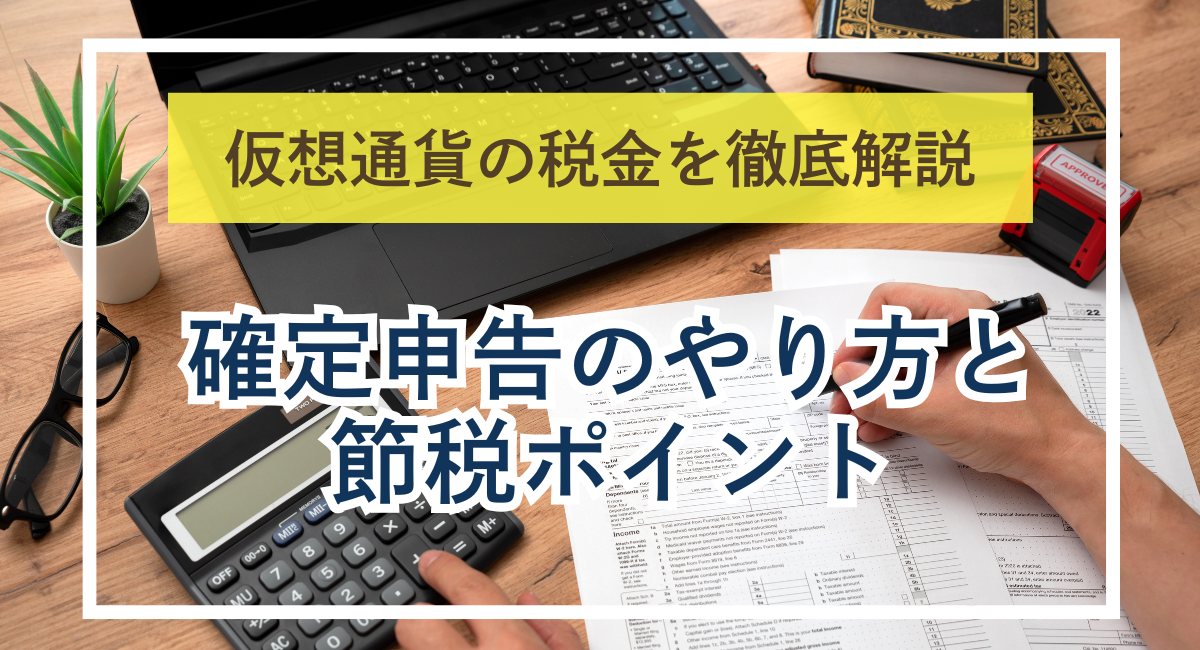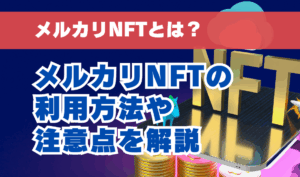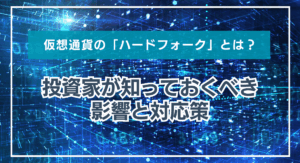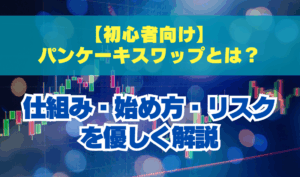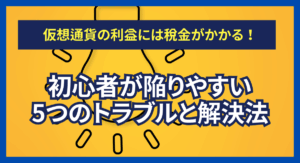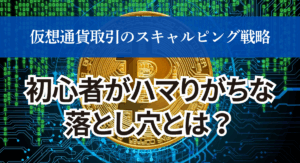ビットコインやイーサリアムをはじめとした仮想通貨(暗号資産)の取引が一般化するにつれ、多くの方が気になるのが「仮想通貨税金」の問題です。
利益が出ても「どこからが課税対象?」「確定申告は必要?」「節税の方法はあるの?」と悩む方も少なくありません。
本記事では、仮想通貨にかかる税金の基本から、確定申告の具体的な方法、そして合法的な節税対策まで、初めての方にもわかりやすく解説します。
仮想通貨にかかる税金の基本

「仮想通貨の利益の所得区分はなに?」「所得の計算方法は?」といった疑問を持っている方が多いと思います。
以下で仮想通貨にかかる税金の基本的知識を勉強していきましょう。
- 仮想通貨の利益は「雑所得」
- 所得金額の計算方法
仮想通貨の利益は「雑所得」
日本において、仮想通貨で得た利益は雑所得(総合課税)として扱われます。
つまり、仮想通貨を「売却」・「他の通貨に交換」・「モノやサービスを購入」した場合、その差益が課税対象となります。
【課税対象となる例】
- 仮想通貨を売却して円に換えた
- 仮想通貨で他の仮想通貨を購入した
- 仮想通貨で商品を購入した
- マイニング報酬を得た
例えば、100万円でBTCを購入した後に150万円まで値上がりしたとしても、売却するまでは利益確定されないので税金を支払う必要はありません。
所得金額の計算方法
仮想通貨の所得金額は以下の式で求められます。
所得金額=収入金額(売却額など)ー必要経費(取得価格や手数料など)
【例】
1ETHを30万円で購入し、40万円で売却した場合
→ 収入金額:40万円、取得価格:30万円
→ 所得金額:10万円(課税対象)
この場合、差額の10万円が課税対象の所得となります。
仮想通貨の確定申告のやり方

仮想通貨の取引で得た雑所得が年間で20万円を超える場合、確定申告が必要になります(給与所得者の場合)。
自営業者やフリーランスの方は、仮想通貨の利益に関わらず、すべての所得を申告しなければなりません。
また、ふるさと納税や医療費控除などで確定申告を行う方は、仮想通貨の年間利益が20万円以下でも併せて申告が必要です。
以下で、確定申告の具体的な申告方法について解説していきます。
確定申告の期間と提出方法
- 申告時期:毎年2月16日〜3月15日
- 申告方法:税務署へ持参、郵送、e-Tax(電子申告)
確定申告は、1年間の所得の情報について、翌年の2月16日〜3月15日の間に申告します。
申告方法は、税務署へ持参・郵送・e-TAX(電子申告)の3パターンですが、おすすめはe-TAX(電子申告)です。
e-TAX(電子申告)を利用すれば、スマホで簡単に申告可能で、提出書類も削減できます。
仮想通貨の収支を記録する
正確な申告を行うためには、日々の取引履歴をしっかり記録しておくことが重要です。
具体的には以下のような情報が必要になります。
- 取引日
- 取引内容(売買・交換・使用)
- 通貨の種類
- 数量
- 約定価格(円換算)
- 手数料
- 取引相手(取引所・ウォレット)
取引回数が少ない方は、個人的に記録しておくだけでも問題ないでしょうが、仮想通貨取引が多い方には、損益計算ツール(Cryptact、Gtaxなど)の利用もおすすめです。
仮想通貨税金の計算例

ここで、仮想通貨投資によって得た利益にかかる実際の税金を計算していきましょう。
事例
- 1BTCを800万円で購入
- 同年中に1,000万円で売却
- 手数料6万円
この場合、利益(雑所得)は以下のとおりです。
利益(雑所得)=1,000万円ー800万円ー6万円=194万円
課税対象額は194万円で、これに所得税+住民税がかかります。
雑所得は総合課税のため、他の所得と合算され、以下の累進課税が適用されます。
| 所得金額 | 所得税率 | 住民税率 | 合計税率 |
| 195万円未満 | 5% | 10% | 15% |
| 195万円以上330万円未満 | 10% | 10% | 20% |
| 330万円以上695万円未満 | 20% | 10% | 30% |
| 695万円以上900万円未満 | 23% | 10% | 33% |
| 900万円以上1,800万円未満 | 33% | 10% | 43% |
| 1,800万円以上 | 40〜45% | 10% | 最大55% |
利益(雑所得)が194万円なので、194万円✖️5%=9.7万円(所得税) 194万円✖️10%=19.4万円(住民税)
合計で29.1万円の税金がかかる計算になります。
また、仮想通貨で大きな利益が出た場合、最大55%の税金がかかることもあるのです。
株式投資で得た利益にかかる税金は約20%なので、仮想通貨投資の税金が大きいことが分かると思います。
しかも、株式投資はNISAに対応しており指定範囲内なら利益が非課税になりますが、仮想通貨は現在のところNISAに対応していないので利益全てに税金がかかります。
知っておきたい節税対策

仮想通貨はNISAに対応しておらず、利益が大きくなるほど所得税率が高くなるので、節税対策が必須です。
- 経費をしっかり計上する
- 利益の分散と売却タイミング
- 長期保有する
経費をしっかり計上する
仮想通貨取引にかかった必要経費をきちんと記録・証明することで、課税所得を減らせます。
【計上可能な経費の例】
- 取引手数料
- 専用PCやスマホの購入費(用途による)
- 仮想通貨関連書籍
- 有料情報サービス利用料
- 会計ソフトや損益計算ツールの費用
仮想通貨投資用のPCや学習用の書籍や有料商材なども経費として計上できます。
数が多くなると計算がややこしくなるので、損益計算ツールなどを利用しての管理がおすすめです。
利益の分散と売却タイミング
年末にまとめて売却すると課税対象が大きくなるため、複数年に分けて利益を出すことで所得の分散が可能です。
また、年収が少ない年に売却することで、税率を下げる工夫も有効でしょう。
長期保有する
仮想通貨をすぐに売らずに長期保有することで課税を将来に先送りできます。
将来的な制度変更に備える意味でも、課税を先送りにすることには意味があります。
日本は利益に最大で55%の税金がかかるなど、世界でも仮想通貨の税金が高い国の一つです。
将来的には日本の仮想通貨にかかる税金制度が見直され、税率が低くなる可能性もあるでしょう。
仮想通貨の税金制度に関するよくある質問
最後に、仮想通貨の税金制度に関してよく寄せられる質問に回答していきます。
- 海外取引所の取引も申告が必要?
- NFTやDeFiの収益はどう扱われる?
海外取引所の取引も申告が必要?
海外取引所での取引も申告が必要です。
日本国内に住む限り、全世界所得課税の原則により、海外での取引も日本で申告する義務があります。
NFTやDeFiの収益はどう扱われる?
NFTの売買やDeFiによる利回り収入も、原則として雑所得に区分されます。
ただし、内容によっては事業所得や譲渡所得になる可能性もあるため、詳細は税理士への相談を推奨します。
まとめ:年間20万円以上の利益が出たら確定申告をしよう
仮想通貨は投資として魅力的な一方で、「税金」のルールが非常に重要です。
以下のポイントを押さえておくことで、トラブルを避け、より効果的な資産運用が可能になります。
- 仮想通貨で得た利益は雑所得として課税対象
- 年間20万円以上の利益がある場合、確定申告が必要
- 正確な記録と自動ツールの活用がカギ
- 経費計上やタイミング調整で節税も可能
特に2023年以降は仮想通貨取引に対する税務署の監視も強化されており、「申告漏れ=脱税」扱いになるケースも増えています。
自己判断せず、適切な申告・節税を行うことで安心して仮想通貨投資を楽しみましょう。