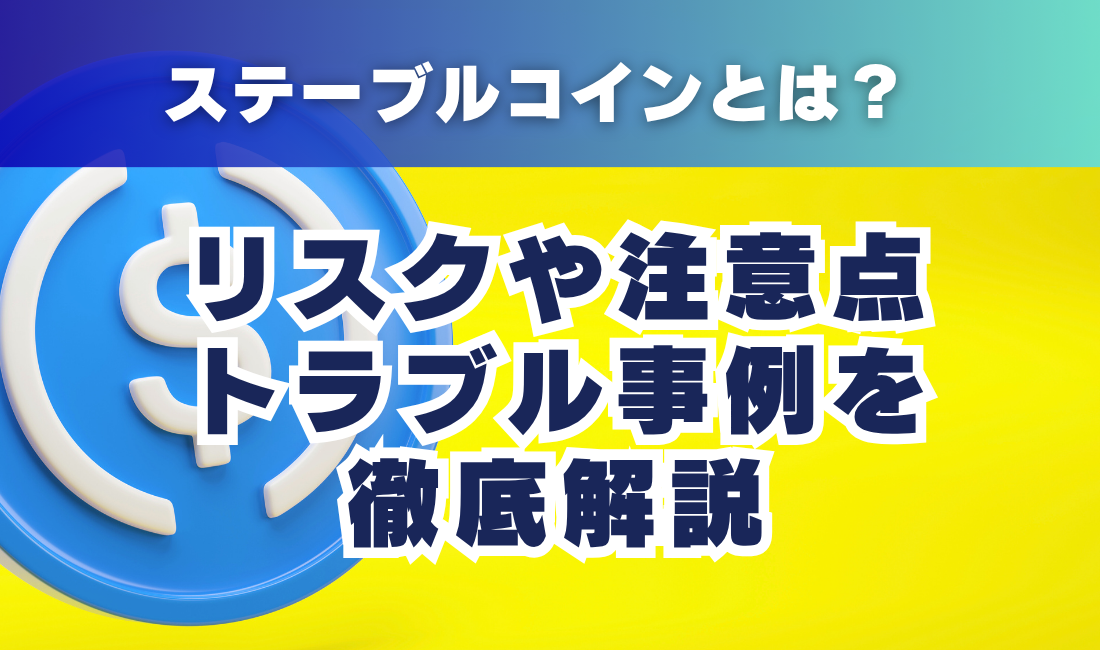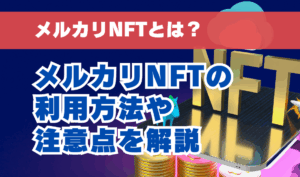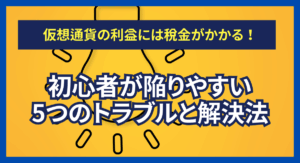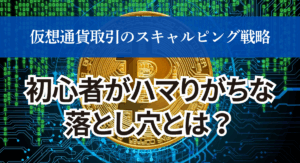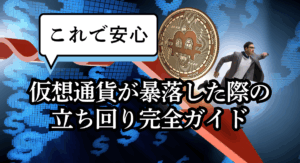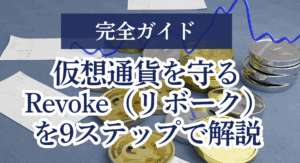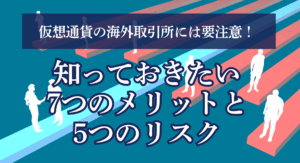仮想通貨市場で価格の安定性を持つステーブルコインは、ビットコインやイーサリアムのような価格変動の激しい暗号資産とは異なり、法定通貨や資産と価値を連動させることで、安定した取引手段として広く利用されています。
また、国内大手取引所のSBI VCトレードが日本国内で初めて主要ステーブルコイン『USDC』の取り扱いを開始したこともあり、注目が高まっています。
しかし、ステーブルコインは本当に安全なのでしょうか?
実は、発行元の信頼性や規制の影響、ディペッグ(価値乖離)のリスクなど、慎重に検討すべきポイントが多く存在します。
本記事では、ステーブルコインの仕組みや種類を解説しつつ、リスクや注意点、実際に発生したトラブル事例を詳しく紹介します。
ステーブルコインを安心して活用するためのポイントも解説するので、ぜひ最後までお読みくださいね。
ステーブルコインとは?
ステーブルコインは、法定通貨(例:米ドル)や資産(金/銀/プラチナなど)と価値を連動させることで、価格の安定性を保つ暗号資産の一種です。
主に法定通貨担保型(USDT、USDC)、暗号資産担保型(DAI)、アルゴリズム型(USTなど)の3種類があります。
①法定通貨担保型: 発行元が米ドルや円などの法定通貨を銀行口座に保管し、その額に応じてステーブルコインを発行する仕組み。USDT(Tether)やUSDC(USD Coin)が代表例で、価格が安定しやすいものの、発行元の信頼性や規制リスクが伴う。
②暗号資産担保型: イーサリアムなどの暗号資産を担保として預け、その価値に応じてステーブルコインを発行する仕組み。代表例のDAI(MakerDAO)は分散型で管理されますが、担保資産の価格変動により安定性が損なわれる可能性がある。
③アルゴリズム型: 特定のアルゴリズムを使って供給量を調整し、法定通貨と連動するように設計されたステーブルコイン。UST(TerraUSD)の崩壊のように、市場の信頼を失うと暴落しやすく、リスクが高いとされている。
ステーブルコインは決済や送金、DeFi(分散型金融)など幅広い用途で利用されています。価格変動が少ないため、仮想通貨市場でのリスクヘッジとしても使われます。
しかし、発行元の透明性や規制リスク、ハッキング被害などの懸念もあります。特に、2022年のUST崩壊のように、アルゴリズム型ステーブルコインは仕組みの特性上、価格維持が困難になりやすく、他のタイプよりもリスクが高いとされています。
また法定通貨担保型でも、Tether(USDT)の準備金問題のように、発行元の信頼性が問われるケースがあります。規制の強化が進む中、政府発行の「CBDC(中央銀行デジタル通貨)」との競争激化もリスクとして指摘されることもあります。
本記事では、そんなステーブルコインの安全性やリスク、注意点を徹底解説していきます。
ステーブルコインは本当に安全?
ステーブルコインは、法定通貨や資産と価値を連動させることで価格の安定性を保つよう設計されており、一般的な仮想通貨と比べるとリスクは低いとされています。
特に、法定通貨担保型のステーブルコインは、裏付けとなる資産が確保されているため、価格の大幅な変動が起こりにくいのが特徴です。
また、送金や決済、DeFi(分散型金融)など、幅広い用途で利用されており、暗号資産市場における安定的な手段として重宝されています。
しかし、すべてのステーブルコインが安全とは言い切れません。
発行元の透明性や規制の影響、ハッキングリスクなど、注意すべき点も多く存在します。
特に、アルゴリズム型のステーブルコインは市場の信頼に依存するため、価格維持の仕組みが崩れると一気に暴落する危険性があります。
基本的には安定性の高い資産ですが、リスクを理解せずに利用すると予期せぬ損失につながる可能性もあります。
「ステーブルコインのリスクや注意点」で、具体的なリスクやトラブル事例について詳しく解説していきますのでぜひチェックしてくださいね。
ステーブルコインのリスクや注意点
ここからは、ステーブルコインのリスクや注意点を詳しく解説していきます。
「ステーブルコインって本当に安全なの?注意点はないの?」と気になる方はぜひお読みくださいね。
1. 発行元の信頼性と準備金リスク
性質上、法定通貨担保型のステーブルコインは、発行元が十分な準備金を保有しているかどうかが価格の安定性に直結します。
しかし、過去にはTether(USDT)が準備金の透明性を疑問視されたことがあり、一部の投資家から不安視される場面もありました。
監査報告を公開しているプロジェクトを選ぶなど、発行元の信頼性をチェックすることが重要です。
基本的には、時価総額が高く、流動性の高いステーブルコインを選ぶのが良いでしょう。
2. 規制リスクと取引制限の可能性
ステーブルコインは政府や規制当局の監視対象となることが多く、特に中央集権的な発行元が管理するコインは、規制の影響を大きく受ける可能性があります。
実際にBUSD(Binance USD)は、米国証券取引委員会(SEC)の規制によって発行が停止されました。
今後も各国で規制が強化される可能性があるため、規制リスクを考慮して運用する必要があります。
3. スマートコントラクトや取引所のリスク
暗号資産担保型のステーブルコインはスマートコントラクトによって管理されますが、ハッキングやコードの脆弱性によって資産が流出するリスクがあります。
また、取引所にステーブルコインを預けたままにしていると、取引所の破綻(例:FTX破綻)によって出金できなくなる可能性もあります。
長期間保管する場合は、自身のウォレットに移して管理するのが安全です。
ただし、これはステーブルコインのみに限らず多くの仮想通貨に共通して言えるリスクであるので、日頃からセキュリティ意識を高く持って仮想通貨投資を行うことが大切です。
4. ディペッグ(Depeg)のリスク
ステーブルコインは決まった価値を維持するよう設計されていますが、上記に挙げたような要因が理由でこのバランスが崩れ、ディペッグ(価格乖離)が発生するリスクがあります。
通常、ステーブルコインは法定通貨や暗号資産、またはアルゴリズムによって価値を安定させるよう設計されていますが、市場の変動や管理上の問題が発生すると、価格が本来意図された価格を下回ったり上回ったりすることがあります。
ディペッグは、主に準備金不足、発行元の信頼低下、市場の急激な売り圧力などによって引き起こされます
一度ディペッグが発生すると、投資家の不安が高まり、さらに売りが加速することで価格の乖離が深刻化する場合があります。ステーブルコインの安定性を維持するためには、十分な準備金と信頼性の高い管理体制が不可欠です。
次からは、ステーブルコインに関する実際のトラブル事例を解説していきます。
ステーブルコインのトラブル事例
ここからは、ステーブルコインのトラブル事例を解説していきます。
必ずしも「ステーブルコイン=安全」ということではない点に注意が必要です。
TerraUSD(UST)の崩壊(2022年)
TerraUSD(UST)はアルゴリズム型ステーブルコインで、LUNAトークンと連動する仕組みで価格を維持していました。
当時は約180億ドル相当が市場に流通しており、当時のステーブルコイン市場で3位という圧倒的なポジションを誇っていました。
しかし、売り圧力が急増したことでシステムが機能しなくなり、USTは1ドルの価値を維持できず暴落。これにより、USTとLUNAの両方が崩壊し、多くの投資家が甚大な損失を被りました。
2022年5月9日:USTは0.98ドル付近まで下落
2022年5月10日:ディペッグが深刻化し、0.80ドルを下回る
2022年5月11日以降:市場のパニックが拡大し、価格は急落
2022年5月13日:USTは0.10ドル以下に下落 その後も回復できず、ほぼ無価値になり、ステーブルコインとしての機能を完全に失う。(現在に至る。)
この事件は「ステーブルコインの安全性」に対する大きな警鐘となり、アルゴリズム型ステーブルコインのリスクが広く認識されるきっかけとなりました。
このように、時価総額を大きく市場に多く流通しているステーブルコインでもわずか数日で価値がなくなってしまう危険性を孕んでいると言えるでしょう。
2. USDCのディペッグ(2023年)
2023年3月、シリコンバレー銀行(SVB)の破綻を受けて、法定通貨担保型ステーブルコインであるUSDCがディペッグを起こしました。
USDCの発行元であるCircleは、準備金の一部をSVBに預けていましたが、銀行の破綻によって資金の回収が一時的に困難になり、市場の不安が高まりました。
その結果、USDCの価格は一時0.87ドルまで約13%の下落を見せ、多くの投資家が混乱しました。
価格が安定していると言われてるステーブルコインで13%もの下落は衝撃的ですね。
この事件は、法定通貨担保型のステーブルコインであっても、銀行システムの影響を受ける可能性があることを示した重要な事例です。
3. Tether(USDT)の準備金透明性問題
USDTは最も広く利用されているステーブルコインですが、発行元であるTether社の準備金管理に関する透明性が長年問題視されています。
特に、過去に「USDTの準備金が100%法定通貨で担保されているのか?」という疑念が持たれ、Tether社は当初、詳細な監査報告を公開していませんでした。
この不透明性が原因で、一部の市場ではUSDTのディペッグが発生したこともあります。その後、Tether社は準備金の内訳を公表するようになりましたが、中央集権的な発行元の信頼性がステーブルコインの安定性に直結することを示した事例となりました。
また、現在においてもTether社は定期的なレポートやアテステーションを通じて透明性を向上させようと努力していますが、完全な独立監査の実施や準備金の詳細な内訳の開示が求められており、依然として議論が続いています。
仮想通貨市場全体の安定性や信頼性に関わるため、今後もTetherの動向や規制当局の対応に注目が必要です。
本記事のまとめ
ステーブルコインは価格の安定性を特徴とする暗号資産であり、法定通貨との連動によって仮想通貨市場のリスクヘッジや決済手段として広く活用されています。
しかし、本記事で解説したように、ステーブルコインにもさまざまなリスクが存在し、必ずしも「完全に安全」とは言えません。
ステーブルコインを安全に利用するためには、発行元の信頼性を確認し、分散管理を徹底し、最新の規制や市場動向をチェックすることが重要です。
特定のステーブルコインに依存せず、リスク分散を意識することで、不測の事態に備えることができます。
価格が安定しているからといって「絶対に安全」と思い込まず、常に慎重な姿勢で運用することが求められます。